人手不足対策として実用化の動きが進んでいる介護ロボット
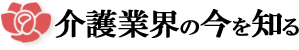
介護業界の人手不足の現状は、まさに先進的技術の開発が得意な日本が解決できる分野です。介護ロボットについては、安全性など課題点も多く残りますが、これから開発が着実に進められていくでしょう。しかし、まだまだ研究開発が思うように進まず、介護ロボットの実用化が先延ばしになっている部分もあります。また介護ロボットは産官学連携ベンチャーという形で、より身近なものとなっています。そして、介護事業者や介助者の負担を大幅に軽減する効果が見込めるでしょう。注目されている介護ロボットを含めた、介護業界の展開について考えてみます。
「公益財団法人介護労働安定センター」が実施した介護労働実態調査では、大半の介護施設で人手不足が問題になっているとの回答がでているのです。介護職員の負担は増え続けている現実が、浮き彫りとなりました。やはり、人手不足では介護サービスの質の低下が起こりうる現状は否めません。そこで、介護ロボットが問題解決の糸口となるようです。
介護施設の経営側から見ても、人材は欲しいが人件費が増えると経営的にも厳しい現状を生むことが分かっています。この人件費が削減できれば、利用料金を抑えられ施設利用者へ還元できるかもしれないのです。将来的に介護ロボットが、人間のように介護支援や利用者とのふれ合いができるようになれば、ますます明るい未来が待っていると言えるでしょう。
介護ロボットの利用については、経済産業省と厚生労働省が2012年に「ロボット技術の介護利用における重点分野」と位置付けました。そこで今後、要介護者の増加によって介護ロボットの社会的必要性が高まることを予測し、研究開発に力を入れ始めました。
経済産業省と厚生労働省が「ロボット技術の介護利用における重点分野」としたため、各企業や研究機関はロボット介護機器の開発を進めています。例えば、装着可否の移乗介助機器、屋外内型の移動支援機器、排泄支援機器、介護施設型や在宅介護型の見守り支援機器、入浴支援機器などの様々な重点分野があるのです。ここで言う介護ロボットは、認知症高齢者を見守る技術や、要介護者の自立支援技術など、介助者の負担軽減のために活躍が期待できるものがほとんどです。人と同じような動きや見た目ではなく、介助を支援する機器といった雰囲気となります。
介護ロボットの導入により介護のあり方も変化し、介助者の負担を減らすための実用化が進んでいます。これからさらに深刻になると予想されている老老介護も、地域包括支援システムにおける在宅介護が要になるようです。
介護ロボットが家庭へ普及するには、一般家庭が購入できる販売価格が理想です。そこまでには、まだ時間を要することにはなります。しかし、購入可能な価格となり一般家庭での利用が安易となれば、家電と同じように最初は浸透しにくくても、時間とともに普及していく日が将来やってくるでしょう。


現職からの転職を考えた時に重要なことは、仕事を探す環境と方法です。まずは、現職を続けながら転職先を探しましょう。探す際の求人媒体も、最近では数多くあります。様々な求人媒体の特徴を紹介します。

日本では高齢者が増え、高齢社会への対策が大きな課題となっています。その中でも、介護業界での人手不足は特に問題視されているのです。ではなぜ人手不足が起こっているのでしょうか。原因を詳しく見ていきましょう。

介護職の離職者のほとんどは、結婚や出産などをきっかけに退職をしているのです。そこで、この貴重な人材を確保するために「再就職準備金制度」ができました。さらに様々な再就職支援も始まっているのです。