人手不足による介護業界の打開策、再就職支援について
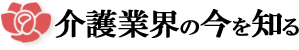
人手不足に悩まされている介護業界。国や事業者などが率先して、人手不足を改善しようと対策を講じているところです。現在、日本の高齢者数も介護施設の利用者数も増え、これからますます介護職のニーズが高まる状況です。また厚生労働省は、2025年には253万人もの介護人材が必要になると見積もっています。実際のところ、介護に携わる人材も増加はしたものの、まだまだ需要を満たしてはいません。有効求人倍率も上昇傾向ですが、特に都市部での介護人材不足は懸念材料です。今後は介護人材確保のための対策が必要で、離職した介護職員の再就職が注目されています。
介護業界での人手不足に対して、新たな動きがでてきました。何らかの理由で離職をした介護職員などへの、再就職支援を行なおうとしているのです。現在の主な再就職支援策は主に2つあります。
1つ目は、離職した人に向けた知識や技術の研修です。例えば埼玉県では、3日間の基礎研修と職場体験を盛り込んだ「潜在介護職員復職支援事業」を実施し、研修後は体験先に就職することもできるようにしています。東京都でも職場体験後に、「介護職員初任者研修資格」の取得支援を行ない、介護業界への再就職を促します。
2つ目は、ハローワークや福祉人材センターでのマッチング支援対策です。各都道府県では、介護施設に再就職できるよう求人情報の開拓や、介護資格取得に関する相談窓口にキャリア支援専門員を設け、再就職を全面的にフォローしています。
さらに自治体や福祉団体だけでなく、介護事業者も再就職支援策を打ち出し、復職支援プログラムを独自に立てています。このような講習や実践セミナーが随時開催され、最終的には雇用につながっていく仕組みを作っているのです。
介護職員の人材確保のための対策として、厚生労働省は離職した人材に対する「再就職準備金制度」での貸付を打ちだしました。この制度の対象者は、介護職員経験が1年以上ある離職者で、介護福祉士など知識や技術を保有する人。そして、都道府県社会福祉協議会が運営する福祉人材センターへの登録も、必須となっています。そしてこの制度を実施できるのは、都道府県や都道府県が認める団体に限られています。
貸付上限額は1回20万円で、子どもの預け先を探す際の活動費や、介護に関わる情報収集や講習会などの諸費用、転居を伴う場合の転居費用、通勤用の自転車やバイクの購入費などに利用できます。また、制度利用者にとってうれしい内容があります。再就職後、2年間介護職員として継続して働くことで、準備金の返還義務が免除されるのです。これは、再就職者と介護業界の双方にとって一役かっていくこととなるでしょう。


現職からの転職を考えた時に重要なことは、仕事を探す環境と方法です。まずは、現職を続けながら転職先を探しましょう。探す際の求人媒体も、最近では数多くあります。様々な求人媒体の特徴を紹介します。

日本では高齢者が増え、高齢社会への対策が大きな課題となっています。その中でも、介護業界での人手不足は特に問題視されているのです。ではなぜ人手不足が起こっているのでしょうか。原因を詳しく見ていきましょう。

介護職の離職者のほとんどは、結婚や出産などをきっかけに退職をしているのです。そこで、この貴重な人材を確保するために「再就職準備金制度」ができました。さらに様々な再就職支援も始まっているのです。